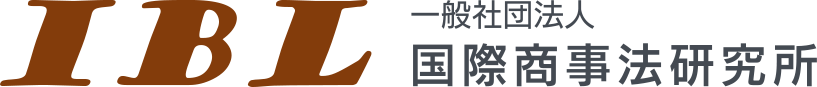2025年10月17日公開
中国企業法務の軌跡(13)~中国にとってディールとは~
J&Cドリームアソシエイツ 大澤頼人
1.ディールの失敗経験が原動力
中国各地を出張していると日本や欧米が1945年以前に建てた建物をよく見ます。日本や欧米列強の政府機関が建てた建物が中国の地方政府によって転用されていることもあります。また、かつての外国人居留地であった旧租界には民間企業や民間人が建てた建物があり、今では中国人の住居やレストランなどの商業施設に転用されているところもあります。特に歴史的な痕跡を残す意味がある建物には金属板のプレート等による説明があります。私はこれらの建物が違和感なく中国の官庁街や住宅街の中に納まっている風景が好きでした。上海、青島、天津などの旧租界は有名で観光客も多いようですが、それらの建物は中国が日本や欧米列強の侵攻を受け、その後のディールで敗北した歴史的教訓を継承させるために残されている面もあります。
例えば香港。香港は1842年、アヘン戦争のあと中国清王朝(以下、清王朝といいます)とイギリスとの間のディールによって締結された南京条約によってイギリスの植民地になります。中国ではイギリスとのディールによって清王朝が領土の支配権の一部を失ったことを教訓にしており、今でも政府コメントで引用されることがあります。近代的な香港の街中には今でもその当時のイギリスの建物が残されています。
例えば台湾、遼東半島、澎湖諸島。これらの領土は1895年、日清戦争のあと清王朝と日本との間のディールによって締結された下関条約により日本へ割譲されます。この経緯は中国共産党が言う「一つの中国」の根拠にもなっていますが、台湾は共産党と清王朝には継続性がないから根拠にならないと反論しています。いずれにしても清王朝が日本とのディールの結果、領土の一部を失った事実は残ります。遼東半島の大都市である大連は日中戦争による日本の植民地時代を含めて日本が建造した建物が幾つも残っています。台湾も然りです。
例えば上海。上海は先の南京条約によって形成されたイギリス租界から始まります。当時の上海は小さな漁村で上海県(今の上海市)によって管理されていました。租界によって上海県には土地賃貸料、その他の税収入があります。1845年、イギリスは上海県にアメリカ租界、フランス租界を認めさせる共同租界のディールをしかけ、上海県はこれを認め第一次土地章程が制定されます。それでも租界は中国政府(上海県)の管理であることに違いはありません。ところが管理下と言っても実効支配できておらず、農民等によって構成される小刀会という組織が上海城(今の観光地の豫園)に籠って反乱を続けたりしており、租界の安全を保つことができず、イギリス、フランス、アメリカは共同して上海県とディールを行い、1854年に租界の自治権を認める第二次土地章程が制定されます。しかしながら清王朝の統治権は弱っており、1851年に太平天国の乱が発生し、共同租界を防衛するため租界は上海県から独立した行政組織にする必要がありました。そこで第三次土地章程が制定されます。これによって上海には日本租界ができたり、中国共産党や国民党の組織も生まれたりして当時の国際紛争を反映した魑魅魍魎の世界になります。今では観光名所になっている租界は欧米とのディールによって止むを得ず認められた自治区がスタートだったのです。
例えば山東省の青島市。青島市にはドイツ風の街並みがあります。坂道に沿って立ち並ぶ洋館は神戸の異人館通に似ています。日本は先の下関条約で遼東半島を割譲させますが、ドイツ、フランス、ロシアから首都北京を脅かす危険があるという、いわゆる三国干渉を受け中国に返還することになります。その見返りとして清王朝はドイツに山東半島の権益権を与えます。青島市にドイツ風の街並みがあるのはそのような経緯からです。そのドイツは第一次世界大戦で敗北し、日本に山東省の権益を譲渡します。
例えば黒竜江省の哈爾濱(ハルピン)市。東北三省は清王朝の統治権が及ばず張作霖の軍閥など地域の有力者による群雄割拠エリアでした。そこにロシア革命でロシアから避難してきたロシア人貴族がロシア風の街並みを作ります。そのあとに軍事侵攻した日本が清王朝の愛新覚羅溥儀とディールを行い満州国が作られます。哈爾濱市にはロシアと日本の建物が今でも混在して残っています。ちなみに中国で流行った映画「731」は哈爾濱市が舞台です(映画の評判は良くないようですが)。
このような事例は一部ですが、中国では日本や欧米とのディールの失敗によって国土の一部を失った苦い歴史があり、その象徴が欧米や日本の建築物です。中国の強い領土意識と強かなディール能力はこういう歴史の繰り返しによって醸成されてきたと思います。我々日本人にはない民族の歴史でこの差は大きいと思っています。米国のトランプ氏はディールを好みますがそれは個人的な傾向です。一方、中国人のディールは民族としての責務と考えている節があります。たとえディールで譲歩することがあっても手ぶらでは帰らない強かさや矜持があるので、これからの中国(政府、企業、人)とのディールには心してかからなければならないと思っています。
2.「韜光養晦(とうこうようかい)」でディールを凌ぐ
「韜光養晦」は中国経済の成長の基礎を作った蒋介石の言葉として伝わっていますが、実際には鄧小平自身はこの言葉を使ったことはなく、江沢民が鄧小平の戦略を表現するときに使った言葉のようです。「能力を隠して好機を待つ」という意味ですが、ここに中国の強かさや矜持があります。鄧小平は文化大革命によって疲弊した中国経済を立て直す手段として外国から資本と技術を積極的に導入する改革開放政策を打ち出します。安いコストと広大な市場を求めて外国資本(以下、外資という)が中国になだれ込んだことは皆さんも承知していると思います。外資に頭を下げても外資を受け入れていく。日中戦争によって生まれた反日意識も抑えて日本企業を受け入れていく。徹底した「韜光養晦」です。いつか日本を抜く、米国を抜くという意識があったものと思いますが、日本も米国もそれを信じた人はいなかったと思います。
1989年の第二次天安門事件で経済制裁を受け経済は再び下降しますが、鄧小平思想を受け継いだ江沢民が社会主義市場経済政策を打ち出し外資には税を優遇するなどして再び外資が中国に投資するようになり中国経済は上昇します。中国企業や中国人からすると外資優遇政策には忸怩たる思いがあったのではないかと想像しますが、そこは「韜光養晦」で乗り切ったのでしょう。私はこのころに中国への投資事業に参加しました。外資ウエルカムを肌で感じました。気がつけば日本や欧米にとって中国抜きの経済、中国抜きのサプライチェーンは考えられないようになっていました。それは今もって変わらないでしょう。私は中国のディールの強さを表す言葉と思いつつ、当時はそれに気づかなかったことを今も戒めとして持っています。
3.「積極有所作為」で攻勢的なディールに転じる
胡錦涛は「韜光養晦は国際的なパワー・バランスの包括的な分析を通じて中央政府によって下された戦略的な分析」という評価をしています。そして能力を隠して好機を待つ時期は過ぎたと判断し、「積極的に為すべきことを為す時期が到来した」という「積極有所作為」という戦略に変更します。反日運動や不買運動が起きたのもこの頃です。
中国経済はGDPで日本を抜いて世界第2位まで成長し、中国国内では次は米国を抜くという熱気が生まれました。かつてのディールは外資に対する警戒心(落とし穴があるのではないか…)が強くアジェンダの優先順位も整理されておらず不毛なディールが多々ありましたが、このころから理論武装されたディールになる本当の意味でのディールができるようになってきました。かつては国有企業中心の「国進民退」でしたが、このころは中国の投資家が作った民営企業が著しい成長をしてきます(習近平政権では国進民退に戻りますが…)。民営企業は国有企業のように国を背景にしたパワーゲームができません。その代わり外資企業と真正面からディールができる人材をそろえてきました。日本や欧米に留学して語学力のある人材、海外で研究開発を経験した研究者や技術者などはディールを支えた優秀な人材です。
このディールを支えた原動力のひとつが法律の整備です。中国は日本と同じ成文法の国ですので、中国の法律の整備は日本の法律家や弁護士が貢献しました。また司法試験も日本と同じ統一司法試験という国家試験になり優秀な法律実務家が生まれ始めます。彼らはディールに同席することが多くなりました。
もうひとつの原動力は豊富な資本です。当初は外国の他人資本によって始まった中国経済ですが、いつの間にか自己資本で経営できるようになってきました。合弁会社であっても中国側の目的は資金調達よりも外資企業が持っている技術力やサプライチェーンの獲得です。これに気づかず安易に技術供与をする外資企業は今もって絶えません。中国の強かさ(したたかさ)に気づかないのでしょうか。ディールでは技術移転や会社の意思決定の仕組みに比重が移っているはずです。
3.「積極有所作為」で攻勢的なディールに転じる
胡錦涛の後を引き継いだのが習近平氏です。この時すでに中国のGDPは日本を引き離しており、米国を追い抜く百年に一度のチャンスが来たという自信に満ち溢れていました。国家主席や共産党総書記の任期も撤廃し習近平独裁政権が誕生します。しかしながらゼロコロナ政策で中国の経済は急降下し今もって上昇する気配はありません。ところが米国に誕生したトランプ政権は、国内経済に比重を移し、国内経済の障害になる外国製品に高関税を課す政策をとります。当然、一番の標的は中国です。関税政策以外に通商法第301条などを駆使した制裁措置を取ります。おそらくトランプ氏は中国が根を上げると思っているのでしょう。制裁を加えることで米国が優位なカードをきれると思っているのかもしれません。中国がディールで追い詰められ相手の条件をのんだのは過去のこと。中国は歴史の教訓から自らゲームオーバーを宣言しないでしょう。中国はこういう日のために中南米、アフリカ、アジア、EUと多角的な外交を進め、ロシアや北朝鮮とは同盟的な関係を形成してきています。特に一帯一路政策は成功しているとは言えませんが米国が抜けた後を埋めていきます。軍事力を強化し、台湾を軍事力で併合できるところまで来ています。また半導体の製造に必要なレアアースの市場を支配しています。
中国のディールの強かさは歴史の結果によるもので民族的な責務という覚悟が窺えます。中国とのディールではこのことを忘れないようにしなければなりません。
<筆者プロフィール>
大澤頼人(おおさわ・よりひと)
伊藤ハムにおいて約 30 年間企業法務に携わる中で、 1997 年から中国事業にかかわる。同社法務部長(2000 年~2013 年)、同社中国常駐代表機構一般代表(2002 年)、同社中国子会社の董事、監事等を経て、2013 年に J&C ドリームアソシエイツを設立し代表に就任。日本企業の中国ビジネスやグローバルガバナンス体制作りを支援している。同志社大学法学研究科非常勤講師(2006 年~2022 年)、立教大学法学部非常勤講師(2015 年)、上海交通大学客員教授(2008 年~2011 年)、中国哈爾濱市仲裁委員(2018 年~2023 年)、上場企業の社外監査役なども歴任。