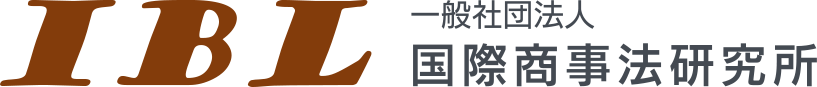2025年06月17日公開
中国企業法務の軌跡(11)~台湾有事(2)~
J&Cドリームアソシエイツ 大澤頼人
6.究極の「まさか」に備える

前回では台湾有事は既に始まっていること、中国はロシアウクライナ戦争のような手法を取らず軍事と非軍事の境界が曖昧なグルーゾーン状態の中で心理戦、世論戦、法律戦を繰り返して台湾版一国二制度を完成させていくこと、台湾政府が一国二制度を承認した場合は人民解放軍が台湾に上陸すること、その際に台湾軍と衝突する可能性は高いがそれは内戦だとする解釈の可能性があること、を解説しました。勿論、何も起きず現状の曖昧な状況が続く可能性もあります。ですから台湾有事は起きないし騒ぎすぎだという意見もあります。
しかしリスクマネジメントというのは、究極の「まさか」に備える経営戦略です。例えば日本は地震が多い国で直近では阪神淡路大震災、東北地方太平洋沖地震、能登半島地震などで甚大な被害を受けた経験から、いつ起きるか分からない南海トラフ巨大地震に備えています。建築基準法も改正されコストの高い耐震構造、免震構造を求められており、住民や会社の従業員には避難訓練もしています。ところが台湾有事のような国際紛争が日本の近海で発生し、日本企業や日本人の安全が脅かされたという経験はありません。そのため台湾有事のイメージをつかむことが難しくコストをかけて究極の「まさか」に備える経営戦略を立てることには躊躇があることは理解できます。私は阪神淡路大震災を経験しましたが、ここで巨大地震が起きることをだれが想像したでしょうか?崩壊するビルや高速道路、生き埋めになって救援を求める声、次々とおきる工場のプロパンガスの爆発など一瞬に崩壊した早朝の修羅場を経験しました。「まさか」に備えるモチベ-ションを維持することは大変難しいことですが、「備えあれば憂いなし」です。
2025年4月、あるコンサルティング会社が調達部門を対象に台湾有事のアンケートを取りました。それによれば調達部門の80%が台湾有事で影響を受けると認識しつつも対策を実施している会社は12%、実施を検討している会社は32%、実施していない会社は54%、分からない会社は2%だったようです。台湾有事は自社の事業は影響を与えるという危機感を持っている会社は少なく、さらに、危機感を持っていても対策を取ってる会社はさらに少ないというのが現状です。一方で台湾有事は起こるという前提で対策を立てている会社は少なからずあります。このような会社はリスクに対する考え方、リスク発生時の組織決定(ガバナンス)、社員や家族の安全配慮、得意先への供給責任、事業の継続や損害を回避するためのコストの使い方など地政学を取り込んだ経営戦略に真剣に取り組んでいました。安倍政権は台湾有事を想定した法律の施行や緊急事態に備える体制を作っていましたが、現政権は曖昧です。から企業は独自でリスク分析をして対応を進めていくことになります。
7.従業員の安全配慮
台湾有事のグレーゾーンのどの段階で生命身体の安全性に対するリスクが具体化するかをピンポイントで示すことは難しいでしょう。グレーゾーン戦は警戒心を低下させる効果がありますから、会社は従業員の安全配慮義務に細心の注意が必要です。
(1)台湾に出向または出張する従業員の安全配慮義務
本社が台湾の会社に出資している場合、日本から経営責任や技術責任を負った従業員が出向していると思い
ます。中には家族連れで出向している方もいます。現在はライトグレーゾーンの段階ですので差し迫った危
険はないでしょう。こういうときこそ生命身体の安全を確保できる場所を確認しておいてほしいと思います。

台湾には全人口を収容できるシェルターがありますので場所を確認しておくと良いでしょう。また、日本と台湾
の間には公式な国交がないため大使館や領事館はなく、それに代わる機関として公益社団法人日本台湾交流協会
が台北と高雄にありますので場所や連絡方法を確認しておくとよいでしょう。
問題は退避が望ましいダークグレーゾーンの場合です。判断基準は会社によって異なると思いますが、台湾有
事に備えている会社は現地従業員の責任者の判断に従うとしているようです。本社と協議する会社もあります
が、現地の危機感は現地にしか分からないところもあります。サイバー攻撃によって電力などの生活インフラが
不安定になった、ATMが稼働しない、中国軍による海上封鎖によって飛行機も船舶が動かない、海底ケーブルが
切断されて本社と通信ができない、などが想定されます。台湾から脱出できない、日本と通信できない、安否が
不明という事態にも備えておくこもも必要です。
また出張者は出向者と異なりホテルを転々としますから居場所を常に本社が把握しておくことが必要です。オ
ープンチケットで出張させている会社もありました。
(2)台湾現地法人の経営責任
現地法人に出向している従業員は出張者と異なり現地法人の経営責任や生産責任を負っています。そこには多
数の現地採用の従業員がいます。安全配慮のためとはいえ現地法人を置いて日本に帰国することに後ろ髪を引か
れる思いがあるでしょう。現地法人には、従業員のほかに製造設備、技術情報、得意先(債権)や仕入先(債務)
など有形無形の資産や負債もあります。本社は現地法人の事業を継続するという前提で日本人従業員の安全配慮
から台湾から退避させることになります。
出向者が日本に帰国しても現地法人の経営が継続できるような組織や人事の制度設計が必要です。それを退避
させるときに決めていては間に合いません。今のようなライトグレーゾーンのときに考えておく必要がありま
す。ある会社では、CEOは現地採用者が就任する、金融システムがトラブったときに備えて給与や退職金に相当
する一定金額を現金で準備する、などの方法を実施している会社もあります。
(3)中国本土に出向または出張する従業員の安全配慮義務
台湾有事は中国側から仕掛けることになりますから、中国本土では監視体制が強化されると予測できます。監視
し拘束できる法律は多数あります。国家安全法、国家機密保護法、国家情報法、行政処罰法、反スパイ法、公民に
よる国家安全危害行為の通報奨励法、反国家分裂法などを挙げることができます。中国政府の台湾政策に関する言
動、軍関係はもちろんのことそれらしい建物への接近や撮影、中国政府関係者との会食など細心の注意が必要で
す。また国防動員法が実施されれば現地法人の従業員は徴兵されますが、会社は従業員の給与の支給などの面で協
力することが求められます。中国本土の現地法人に出向している従業員や出張者の安全のため、この際、社員教育
を見直し、まさかの拘束があった場合のアクションプランを作っておくことが求められます。
(4)台湾では海上封鎖によっては航空機や船舶などによって出国できない場合、サイバー攻撃や海底ケーブルの切
断によって通信ができず安否確認ができない場合、などが想定されます。一方、中国では中国政府の出入国管理
によって出国が制限されることが想定されます。このような「まさか」に備えた本社のバックアップ体制と従業
員教育が必須になります。
8.サプライチェーンの検証
台湾が製造と物流の拠点である場合、台湾有事がダークグレーゾン段階に入ってしまうと台湾国内での製造や物流に支障が生じ、その結果、サプライチェーンが遮断する可能性が高くなります。遮断されてから対応していては間に合いません。
台湾に自社の工場があり、そこで生産された製品が日本や中国あるいは第三国に輸出されている場合、代替生産を考えなければなりません。その工場で生産されている製品が汎用品であれば代替品を見つけることは難しくないと思いますが、技術指導をして製造してきた特注品であれば直ちに代替品を製造できる工場を捜すことは容易ではありません。
台湾に自社工場がないが台湾企業にOEM生産を委託している場合、あるいは台湾企業でしか製造できない製品(例えば半導体関連)の場合も直ちに代替品を入手することは容易ではありません。
このような「まさか」の事態を想定し、サプライチェーンが寸断されない製造戦略のために自社のサプライチェーンを検証しておくことが必要です。サプライチェーンを寸断させないための時間やコストも重要な課題です。規模の大きな会社では、事業部ごとに中国や台湾を組み込んだサプライチェーンがありますから、全体の流れを俯瞰してみることができる組織が必要になります。
9.トランプ地政学
日本企業の成長にとって中国や台湾は重要な拠点です。それは今後も変わらないと思います。一方で、東アジアの地政学は米中対立によって様変わりしています。それは今後も続くでしょう。特にトランプ政権は日本企業の技術支援が中国の経済成長に貢献してきたことを快く思っていません。トランプ政権の関心は自動車、鉄鋼に続き造船業に向かっているようです。地政学から拠点の見直し、サプライチェーンの見直し、などにも経営資源を当てていく必要があると思います。
<筆者プロフィール>
大澤頼人(おおさわ・よりひと)
伊藤ハムにおいて約 30 年間企業法務に携わる中で、 1997 年から中国事業にかかわる。同社法務部長(2000 年~2013 年)、同社中国常駐代表機構一般代表(2002 年)、同社中国子会社の董事、監事等を経て、2013 年に J&C ドリームアソシエイツを設立し代表に就任。日本企業の中国ビジネスやグローバルガバナンス体制作りを支援している。同志社大学法学研究科非常勤講師(2006 年~2022 年)、立教大学法学部非常勤講師(2015 年)、上海交通大学客員教授(2008 年~2011 年)、中国哈爾濱市仲裁委員(2018 年~2023 年)、上場企業の社外監査役なども歴任。