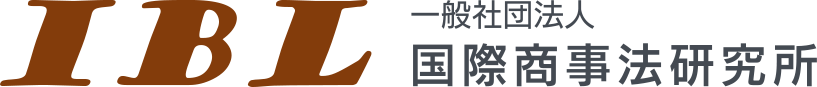2025年05月14日公開
中国企業法務の軌跡(10)~台湾有事(1)~
J&Cドリームアソシエイツ 大澤頼人
1. 台湾と沖縄
沖縄はかつて琉球国という独立した国でしたが、薩摩藩が武力侵攻し、1611年に薩摩藩が支配する「付属国」になり、1879年の明治政府による太政官通達で日本の領土になります。詳しいことは言語学者や民族学者に任せるとして、民俗学的には本土の日本人も琉球人もモンゴロイド系らしいようですが、言語体系は全く異なりユネスコの調査では琉球語は日本語の方言ではなく独立した言語とのことです。このように歴史を遡れば日本が沖縄を武力で併合し文化や制度を日本基準にしたと言えます。
台湾も沖縄に似ているところがあります。今の台湾人は17世紀に福建省や広東省から来た渡来人ですが、先住台湾人は中国大陸に由来する民族ではなくハワイやポリネシアの系統(オーストロネシア系)だったようです。また台湾語は中国からの渡来人の影響で中国の広東語に近い言語ですが、元々の言語は南太平洋の民族の言語に近かったようです。すなわち、台湾は中国大陸に近い位置にありますが、民俗学的にも言語学的にも中国本土とは縁がなかったのです。先住台湾人は国としてまとまっていなかったのでオランダやスペインに支配されますが、その支配から台湾を救ったのは中国人と日本人の間に生まれた鄭成功(日本名田川福松)です。鄭成功は台湾に「東寧国」を建国します。近松門左衛門の人形瑠璃・国姓爺合戦は鄭成功の物語です。
1683年に「東寧国」は清王朝との戦いに敗れ、それを境に福建省や広東省から中国人が台湾に移り住むようになります。沖縄の歴史に似ているところがあります。その清王朝は日清戦争で日本に破れ、1895年の日清講和条約によって日本が台湾を統治するようになります。日本による統治は1945年まで続きます。その後の台湾のことは皆さんもご承知の通り、毛沢東が率いる中国共産党との内戦に敗れた蒋介石率いる国民党が台湾に渡り中華民国は台湾に移転します。暫くは蒋介石の国民党が台湾を牽引しますが強引な政策に反対する民衆の中から1986年に民進党が誕生します。以後、台湾の総統は国民党または民進党から選出されています。なお、台湾の国名は正式には中華民国ですがここでは便宜上台湾と表記します。
2. 台湾有事の論点
第1の論点は台湾の領土権です。中国は、台湾を中国の領土にすること、政治制度は香港やマカオと同じような一国二制度にすると考えています。これに対し、台湾の民進党は一国二制度に反対し現状のままでよいと考えていますが、国民党は一国二制度に賛成しています。なお、台湾の領土は、中華民国の条例(台湾地区と大陸地区の人民関係条例)第2条1項で台湾本島、澎湖諸島、金門島、馬祖島とされています。
第2の論点は一国二制度に移行する方法です。中国は平和的に移行すると言っていますが、2005年に施行された反国家分裂法という法律では非平和的な措置を取る可能性を残しています。
第1の論点ですが、民進党の頼清徳が総統に就任したのは2024年5月20日です。台湾の総統の任期は4年で2期継続して就任できますから、次の2028年の総統選で頼清徳が選任される可能性もあり、その場合は2032年まで民進党政権になります。一方、習近平総書記は台湾併合の「準備」を民進党政権下の2027年までに「平和的に整える」と言っています。一国二制度が「完成する」とは言っていません。中国の政策を理解するときには言葉の使い分けに注意する必要があります。「準備を整える」とはどう意味か私なりに考えみました。
これは第2の論点にも関わることですが、準備は平和的に整えるが台湾併合を完成させる最後の段階では非平和的な手段を選択する可能性を残しているということではないでしょうか。その鍵は台湾国軍の存在です。台湾には米国から技術支援を受け近代的兵器を備えた台湾国軍が存在します。もし、2028年の台湾総統選で国民党から選出された人が総統になれば台湾国軍を解散して台湾併合は平和的に完成する可能性があります。しかし、民進党政権下では台湾国軍と人民解放軍との衝突は避けることはできないでしょう。
この衝突は「国際紛争」と解釈される可能性が高く、そうなれば日本は集団的安全保障または集団的自衛権の行使という課題に直面します。しかし、国民党の政権下であれば台湾国軍を解散する可能性があります。もちろん、それでも台湾国軍の一部が抵抗して武力衝突が発生する可能性はあります。しかし、それは「内紛」として片付けられる可能性があります。台湾が民進党政権か国民党政権かによって武力衝突の評価が異なってくる可能性があります。
香港は1997年7月1日にイギリスから中国に返還され、今後50年間、一国二制度が保証されるとされていますが、1996年の全国人民代表大会で「香港駐軍法」が可決され、今では少数ながら人民解放軍が香港に駐留しています。香港政府は軍隊を持っていなかったので武力衝突は起きませんでした。1989年の第二次天安門事件を思い起こせば、100万人近いデモ隊は人民解放軍によって鎮圧されました。人民解放軍は国内の治安を維持する役目を負っていることが分かります。台湾でも同様なことが起きた場合、人民解放軍と台湾国軍やそれを支援する国民との衝突は「内紛」なのか「国際紛争」なのか評価が分かれるところです。
3. 国論を二分する「92年コンセンサス」
2008年の総統選で国民党の馬英九が総統に就任しました。馬英九は「92年コンセンサス」(中国表記は九二共識)を基礎に中台関係を促進すると発表しました。「92年コンセンサス」というのは、1992年、台湾の海峡交流基金会と中国の海峡両岸関係協会が「一つの中国」を認める合意のことをいいます。口頭で合意されただけで書面はなかったので、しばらくの間、その存在は明らかにされていませんでした。当時の李登輝総統(国民党)もその存在を否定していました。
しかし、2000年に民進党から選出された陳水扁が台湾総統に就任すると国民党の蘇起は「92年コンセンサス」の存在を公表しました。国民党は「ひとつの中国」の意味を「中国はひとつであるがその解釈は各自で異なる」(中国語表記は一中各表)と説明しました。一方、中国側はそのような解釈について議論したことはなく「中国はひとつしない」(中国表記は一中原則)という意味だと反論しています。
2016年に台湾総統に就任した蔡英文、2024年に就任した頼清徳(共に民進党)は共に「92年コンセンサス」の存在を認めていませんが、中国側は台湾の国論を二分する重要なキーワードとして使ってくると考えられます。
4. 認知戦
では中国がいう平和的な台湾併合の準備とはどういうものなのでしょうか。ロシアウクライナ紛争で明らかなように戦争には膨大なコストがかかります。さらに台湾には中国大陸と人間関係が繋がっている人が多くいます。中国としてはコストと人的な犠牲は避けたいでしょう。特に中国経済はいまだに回復していませんから戦争は国民に負担をかけます。
日本人は気付かないことですが、中国本土では台湾併合は当然だと言う人は圧倒的に多くいます。私が知る限り民主派と言われる人たちでも台湾併合を肯定します。しかし、人的被害が出ることまで想定している人は少ないでしょう。もしそのような事態になれば習近平政権に批判が集中し習近平政権の安定を脅かすことにもなりかねません。そこで中国は、「戦わずして勝つ」(孫子の兵法)認知戦を繰り返すことにしました。認知戦では人的な犠牲はなく、コストは戦争よりはるかに低いでしょう。
中国の認知戦は、心理戦、世論戦、法律戦という三つの戦いで構成されているようです(これを中国では三戦といいます)。民解放軍が台湾に上陸するまでの間、まるでサラミソーセージを切るように少しずつ状況を切り開いていくと考えられます(これをサラミ戦術といいます)。人民解放軍が台湾に上陸するまでは軍事と非軍事の境界が曖昧な状態になります。このような状態をグレーゾーン戦といいます。

心理戦の具体例としては、台湾周辺での軍事訓練、海底ケーブルの切断、サイバー攻撃、海警局の海警船による日本の領海侵犯などによって台湾の国民に対し心理的圧 力を与える作戦です。
世論戦は、一国二制度に対する台湾国内での支持率を高めることです。SNSを活用したフェイクニュース、一国二制度に称賛するインフルエンサーのブログ、政府機関や軍に対する中国のスパイ工作などがあります。事実、昨年、軍の幹部や民進党の関係者が中国のスパイ工作に協力したという疑惑で64名が逮捕・起訴されました。
法律戦というのは台湾併合の準備を合法化する法律を施行し執行することを意味します。「反国家分裂法」は台湾独立運動を違法とします。実際に出張や観光で中国に渡航した台湾人が逮捕されたりしています。「海警法」は台湾海峡、パシー海峡、与那国海峡を海上臨時警戒区とし海警船による法執行(船舶の拿捕、船員の逮捕)を可能していますが、国際法上、中国の海上臨時警戒区は認められていません。「国家情報法」は国家情報工作に国民が協力する義務を定めています。この義務は国外にいる中国人にも適用されます。「国防動員法」は台湾有事の際には国民を動員することができる法律で外資系企業に勤務する中国人にも適用され、企業はこれに協力する義務がありますます。そのほかスパイ防止法の執行も気がかりです。
このような認知戦を「準備を整える」期間に繰り返すことで一国二制度を賛成する台湾政権の樹立を考えているのではないでしょうか。
5. 国際紛争から国内紛争への転換
台湾政府が一国二制度を承認していない状態で人民解放軍が台湾上陸を試みれば台湾国軍との武力衝突になります。これを国際紛争と解釈すれば、日本の集団的安全保障や集団的自衛権の行使という重大な局面に直面します。一方、台湾政府が一国二制度と台湾国軍の解散を承認すれば人民解放軍は非軍事的に台湾上陸を果たすことが可能になります。一部で発生する台湾国軍との武力衝突は中国が言う国内紛争になる可能性もあります。
国際紛争であろうと内紛であろうと、台湾や中国に進出している日本企業は事業継続性や従業員の安全性、サプライチェーンの確保、生産活動の継続という課題に直面します。様々な制限で日本にはリアルな情報が入ってきませんが何らかの手を打たなければ業績に大きな影響を与えます。次回に触れてみたいと思います。
<筆者プロフィール>
大澤頼人(おおさわ・よりひと)
伊藤ハムにおいて約 30 年間企業法務に携わる中で、 1997 年から中国事業にかかわる。同社法務部長(2000 年~2013 年)、同社中国常駐代表機構一般代表(2002 年)、同社中国子会社の董事、監事等を経て、2013 年に J&C ドリームアソシエイツを設立し代表に就任。日本企業の中国ビジネスやグローバルガバナンス体制作りを支援している。同志社大学法学研究科非常勤講師(2006 年~2022 年)、立教大学法学部非常勤講師(2015 年)、上海交通大学客員教授(2008 年~2011 年)、中国哈爾濱市仲裁委員(2018 年~2023 年)、上場企業の社外監査役なども歴任。