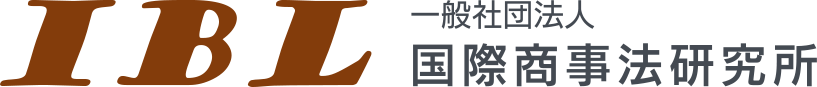2025年10月01日公開
第11回 行政によるAI利活用
Ⅰ 行政によるAI利活用の現状
筆者は県顧問弁護士や豊島区個人情報保護審議会委員として、自治体のAI化を含むデジタル化に関与している1。
行政はますますAIを利活用しており、少なくとも導入率はめざましい。例えば、生成AIを導入済みの団体は、都道府県で87%、指定都市で90%、その他の市区町村で30%となった。実証中、導入予定を含めると、都道府県・指定都市は100%、その他の市区町村は51%が生成AIの導入に向けて取り組んでいる2。
また、生成AI以外を含むAI導入済み団体数は、都道府県・指定都市で100%、その他の市区町村は58%となり、実証中、導入予定、導入検討中を含めると約76%がAIの導入に向けて取り組んでいる。RPAの導入済み団体数は、都道府県が94%、指定都市が100%、その他の市区町村は41%となり、実証中、導入予定、導入検討中を含めると約65%がRPAの導入に向けて取り組んでいる3。AI新法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」も「行政事務の効率化及び高度化を図るため、国の行政機関における人工知能関連技術の積極的な活用を進める」国の責務(4条2項)及び「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し(中略) その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する」地方自治体の責務(5条)を定めた4。
1)行政とAIにつき、松尾剛行『生成AIの法律実務』207頁以下。その他のAIと行政法に関する筆者の研究の一部に、久末弥生編『都市行政の最先端 法学と政治学 からの展望』(日本評論社、2019年)第6章「都市行政とAI・ロボット活用」松尾剛行「行政におけるAI ・ロボットの利用に関する法的考察」情報ネットワーク・ローレビュー第17巻(2019年)92頁以下、松尾剛行「ChatGPT時代の行政におけるAIの利用にあたっての法的課題 AIの利用に伴う透明性の問題(1)」戸籍時報2023年8月号vol.842、松尾剛行「ChatGPT時代の行政におけるAIの利用にあたっての法的課題(2)AIの提供した誤情報への信頼保護及び国家賠償責任」戸籍時報2023年9月号vol.843、松尾剛行「ChatGPT時代の行政におけるAIの利用にあたっての法的課題(3)AIの利活用と民営化や民間委託との比較及び行政はAIとどう付き合うべきか」戸籍時報2023年10月号vol.844、松尾剛行「ChatGPT時代の行政におけるAIの利用にあたっての法的課題(4・完)行政におけるChatGPTの利用実務」戸籍時報2023年11月号vol.846、及び松尾剛行他「行政におけるAI利用の法的課題」都市問題2024年2月号がある。
2)総務省情報流通行政局地域通信振興課自治行政局行政経営支援室「自治体における生成AI導入状況(2025年)
https://www.soumu.go.jp/main_content/001018084.pdf
3)総務省情報流通行政局地域通信振興課自治行政局行政経営支援室 「自治体におけるAI・RPA活用促進(2025年)」https://www.soumu.go.jp/main_content/001018084.pdf
4)AI新法につき松尾剛行「【2025年施行】AI新法とは?AIの研究開発・利活用を推進する法律を分かりやすく解説!」契約ウォッチ2025年7月10日 https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/2025-ai-law/ 参照。
この記事は会員限定コンテンツです。会員に登録いただきますと続きをお読みいただけます。
会員の方はログインして続きをお読みください。

<筆者プロフィール>
松尾剛行(まつお・たかゆき)
桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士(第一東京弁護士会)・ニューヨーク州弁護士、法学博士、学習院大学特別客員教授、慶應義塾大学特任准教授、AIリーガルテック協会(旧AI・契約レビューテクノロジー協会)代表理事。Business Lawyer Award 2025(情報発信部門)受賞